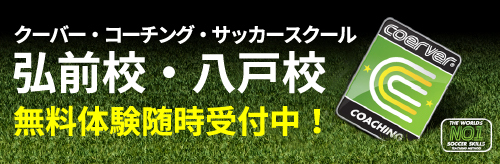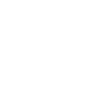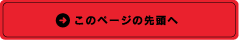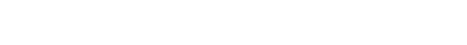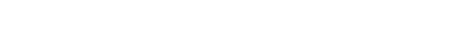NEWS&TOPICS
NEWS&TOPICS
コラム「監督・コーチ・選手たちの言葉から、選手権初優勝までの軌跡を辿る」
2017年02月24日

前口上として
いつまでも止まない雪に苦しめられるような、そんな戦いが続いてきたのが青森山田の選手権での歴史だった。鬼門と呼ばれた三回戦で幾度となく涙をのみ、ベスト16の壁に行く手を阻まれ続けた。ここを乗り越えても、優勝までの道程は遠かった。決勝戦の舞台で敗れ、表彰台を下から眺める苦汁も味わった。
しかし、明けない夜がないように、晴れない空もない。降りしきる雪を踏み固め、飛躍を期し、雌伏の時を経て、彼らはついにその頂へと上り詰めた。

歓喜のピッチから
試合終了の笛の音がスタジアムに鳴り響いた瞬間、ベンチから緑色のユニフォームが一人、また一人とピッチへ飛び出していく。その姿を眼前に捉えながら、黒田監督がコーチらと肩を組んで破顔一笑。ピッチ上では歓喜の雄叫びをあげる青森山田イレブンと、その横でうなだれる前橋育英イレブンが。お互い初優勝を目指し、しのぎを削り合ったが、夢の舞台の上で残酷なまでに描かれたコントラスト。最終スコアは5-0。青森山田の快勝だった。
しかし、スコア以上に両チームの実力差があったと断ずることはできない。前半の決定機の数はむしろ前橋育英の方が勝っていた。では何が勝敗を分けたのか。
黒田監督の苦節ともいえる22年間。そうしてやっと手にした頂点。監督自身の、コーチ陣の、選手たちの言葉から、初優勝までの軌跡を辿る。

栄冠までの道程〜選手の言葉から
「体力と精神力を冬の間に身に付けました。雪があるから今があります(住永)」
「雪国だからこそできる練習もあって、それで足腰が鍛えられるんです(鳴海)」
「厳しい環境の中で成長できました(嵯峨)」
「雪は本当に辛くて、逃げ出したくなるんですけど、それを乗り越えるたびに強くなったと感じました(郷家)」
選手たちが口を揃えてこう話すほど過酷な練習を乗り越えてきた青森山田の面々。だが、中核となるトップチームのメンバーは各々個性が強く、「まとめるのが大変でした」と主将の住永は過去を振り返る。
「我の強い選手が多かったので、やっぱりどうしても『自分、自分』となってしまって。新チームとして動き出した当初は自分の意見をどんどん言うだけで、人の話を聞かない選手が多かった。それが夏のインターハイで負けて、より負けたくないという思いが強くなって、そこからはみんな人の話もよく聞くようになったし、勝つためになんでも吸収しようとし始めました」
そうした中で迎えた高円宮杯チャンピオンシップで見事優勝。日本一の栄冠を手にする。
雪辱を果たし、それまでの努力を確固たる自信へと昇華させた青森山田は、悲願である選手権制覇に向けて動き出す。そこで最も難しかったのが、一度頂点に立ったことによる慢心の顕在化と、モチベーションの維持だった。
「『チャンピオンシップで優勝したから選手権も勝てるんじゃないか』と思ってしまうのが一番怖かった。そこを押しつぶしていかないと(選手権優勝は)絶対に無理だと。これがすごく難しかった(住永)」
しかし、そこは黒田監督が歴戦の経験から裏打ちされた手腕を発揮し、選手たちのモチベーションをコントロールする。
「さすがに落ちる時もあったと思うんですが、監督が『落ちてもいいから本番には同じレベルに持っていく』という方向で調整していました(大久保コーチ)」と、選手らも大きくテンションを落とすことなく、本番に向けてメンタル面を仕上げることができた。
「自分たちのサッカーをやっていれば絶対に勝てる(鳴海)」
「自分たちがやってきたことに自信を持っています(廣末)」
このように、選手がはっきりと自信を持って戦える意義は大きい。 “負けるかもしれない”“勝てないかもしれない”という弱気な思いがあると、少しのミスでも選手は動揺してしまう。前述したように慢心は大敵だが、過信のない自信は大きな武器になる。
同時に懸念されたコンディショニングも、「チャンピオンシップから選手権までの期間が短かったことが逆に良くて、他のチームに比べたら試合勘がなくならないというメリットはありました。それはすごく良かったですし、(チャンピオンシップの決勝で)埼玉スタジアムのピッチでやれたことも良かったですね(住永)」とむしろプラスに転換させることができた。こうして青森山田はチャンピオンシップ優勝からの勢いを落とすことなく、かつ心身ともに万全の状態で選手権に挑むことができた。
そして結果はご存知の通り。高円宮杯チャンピオンシップ&選手権制覇の「二冠チーム」であり、「日本最北端の王者」が誕生したのだった。
(続く)
取材・文 本田悠喜(スポーツライター)

お買い求めの場合はこちらからどうぞ!
→http://www.aomori-goal.com/buy/
>> 一覧に戻る
NEWS&TOPICS
- 2024.04.05
- 今季初勝利!ラインメール青森4選手インタビュー
- 2024.03.04
- 雑誌価格改訂のお知らせ
- 2024.03.02
- ラインメール青森、2024キックオフパーティーを開催
- 2024.02.21
- 今月25日発売予定の「AOMORI GOAL VOL.86」。発売日延期のご案内
- 2024.01.25
- 悲願のJ3昇格へ ラインメール青森、2024シーズン始動
青森県大会情報
- 2024.02.06
- 【第24回地域フットサルチャンピオンズリーグ】に挑むイタチカ八戸
- 2024.01.27
- 第23回東北高等学校新人サッカー選手権大会(男子)
- 2023.12.30
- 第102回全国高校サッカー選手権大会に挑む青森山田高校の選手たちの意気込みを紹介!16~30
- 2023.12.30
- 第102回全国高校サッカー選手権大会に挑む青森山田高校の選手たちの意気込みを紹介!1~15
- 2023.12.23
- JFA全日本フットサル選手権大会東北大会